将棋教室での学びは、子どもたちに論理的思考力や集中力を育む素晴らしい機会ですが、その経験を「情報発信」によってさらに深めることができるのをご存じですか?
今やSNSやブログといった情報発信は、ただのアウトプットではなく、子どもたちが自分の成長を感じ、将棋を通じて新しい学びやつながりを得る大切な手段となっています。
ここでは、将棋教室の情報発信が子どもたちにどのようなメリットをもたらすのかを、3つの観点からご紹介します。
「今日の対局でこんな戦法を使った」「大好きな棋士のこの手筋に挑戦してみた」など、子どもたちの将棋の学びや挑戦を発信することで、思わぬ情報やアドバイスが集まります。情報を受け取るだけでなく、自分から発信することで、将棋への理解がさらに深まります。
例えば:
・同じ戦法を学んでいる仲間がコメントをくれて、別の視点でのアドバイスがもらえる。
・先生や先輩棋士が、より良い手のアイデアやアプローチを教えてくれる。
・将棋に興味を持った子どもの投稿がきっかけで、新しい仲間が将棋教室に参加することも。
発信は「一方通行」ではなく、将棋を学ぶ仲間や将棋ファンとの双方向のコミュニケーションの場になります。
情報発信をすることは、将棋を学んだり対局を振り返ったりするうえで、自分の思考を整理する絶好の機会です。「なぜその一手を指したのか」「どうして負けたのか」を言語化することで、次の対局に活かせる気づきが生まれます。
発信を通じた思考の整理の例:
・対局後に、「この一手が甘かった」と気づき、次に同じ場面でどう指すべきかを考える。
・特定の戦法(矢倉、振り飛車など)を練習した記録を書くことで、得意戦法が徐々に明確になる。
・将棋教室で学んだことを文章にまとめることで、「わかったつもり」を防ぎ、理解を深める。
情報発信を通じて自分の考えを振り返る力は、将棋だけでなく、日常生活や学習面でも役立つ大切なスキルです。
将棋教室での経験を発信し続けることで、子どもたち自身が「どれだけ成長したか」を可視化できます。
初めて覚えた戦法、初めて勝った大会、苦手だった局面を克服した経験など、情報発信はすべて自分だけの「成長のアルバム」となります。
・大会やイベントの結果を発信することで、自分の努力や成果を見える形で残す。
・1年前の投稿を見返して、「こんなに強くなった!」と成長を実感する。
・保護者や将棋教室の先生が、子どもの努力を振り返りながら、次の目標を一緒に設定できる。
成長を記録することで、子どもたちは「自分は頑張っているんだ」という自己肯定感を持ちやすくなり、さらに意欲的に将棋に取り組むようになります。

情報発信が大事なのはわかったけど何から始めればいいの?
「何を発信したらいいの?」と悩む必要はありません。以下のようなテーマで気軽に始めてみましょう
・今日の対局で気づいたことや楽しかったポイント
・将棋教室で学んだ新しい戦法や手筋
・憧れの棋士や目標にしているプレイヤーについて
・将棋に関するイベントや大会の感想
短い文章や簡単な感想でもOK。続けることで発信が自然と習慣になります。
私のNoteはこちらを参照ください。
将棋教室での情報発信は、以下のような力を子どもたちに育みます
・発信を通じて新しい知識や人とのつながりを得る
・対局や学びを振り返る中で思考の整理ができる
・自分の成長を見える形で残し、自信を持てる
「学んだことを発信する」という行動は、子どもたちが将棋を通じて得た学びをさらに深め、将棋を楽しむ力を育てます。そして、情報発信は将棋の上達だけでなく、子どもたちの未来にも必ず役立つスキルです。
ぜひ、将棋教室での経験を記録し、発信することを親子で楽しみながら実践してみてください。それがきっと、次の一手をさらに素晴らしいものにしてくれるはずです!
 高橋海渡の将棋アカデミー
高橋海渡の将棋アカデミー 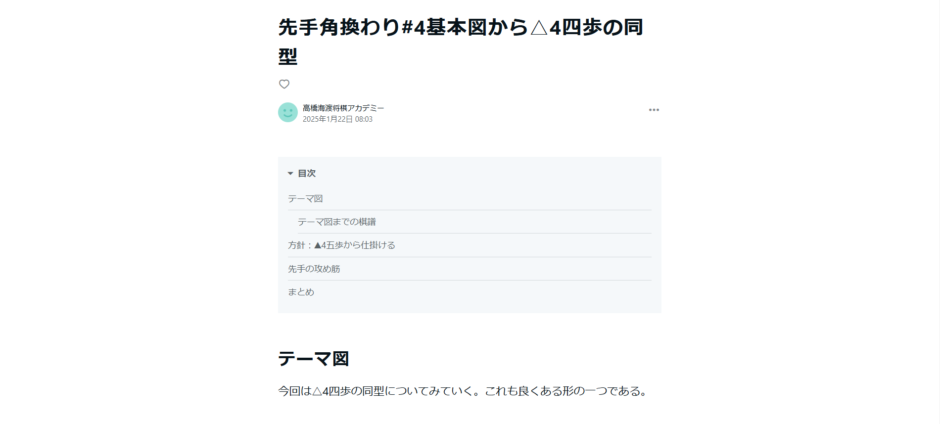



e5juzw